「すき家でネズミの死骸混入」と検索している方は、ニュースやSNSで話題となった衝撃的な投稿を見て、不安や疑問を抱えているのではないでしょうか。
今回の事案は、ゼンショーホールディングスが運営するすき家の店舗で発生した異物混入に関するもので、実際に味噌汁の中にネズミの死骸が混入していたことが確認されました。
初動の遅れや情報公開のタイミングが問題視されたことから、SNS上では「本当にあったのか」「隠蔽ではないか」といった声が相次ぎ、企業の対応姿勢にも注目が集まりました。
この記事では、発端となった投稿内容や、すき家の事実発表、混入の原因、そして講じられた再発防止策までを一つずつ詳しく整理しています。
また、外食業界全体における衛生管理の基準や、もし消費者が異物混入に遭遇した場合の対応方法、相談先としての保健所や消費生活センターについても触れています。
結論として、すき家側は異物混入の事実を認めた上で対策を講じており、再発防止に向けた取り組みが進められています。ただし、消費者としては引き続き企業の対応を見守るとともに、正しい知識をもって行動することが求められます。
本記事が、今回の「すき家でネズミの死骸混入」問題について現状を把握する手助けになれば幸いです。
- 事象発生経緯
- すき家の事実公表内容
- ネズミ混入の原因と衛生管理上の問題点
- 消費者が異物混入に遭遇した場合の
すき家 鳥取南吉方店でネズミの死骸混入が発生

- 味噌汁で発生した事象の経緯
- すき家の事実発表と2ヶ月間かかった理由
- なぜネズミが混入したのか?
- 公表された対策内容
味噌汁で発生した事象の経緯

SNSがきっかけで飲食店の問題が一気に広がるケースは珍しくありません。今回の「すき家でネズミの死骸混入」問題も、最初の火種はGoogleマップ上に投稿されたあるレビューでした。
その投稿には、朝食のみそ汁の中にネズミの死骸が浮かんでいるとされる衝撃的な画像が添えられており、見る人に強烈なインパクトを与えました。とくに、ネズミの大きさや状態がリアルだったため、「AIによるフェイク画像ではないか」という疑念まで巻き起こりました。
ただし、この画像は後に事実であったと判明します。実際、鳥取南吉方店のクチコミとして投稿された内容には具体的な日時(1月21日午前8時頃)が明記されており、単なる誹謗中傷ではない信ぴょう性がありました。
このように、
- 明確な日時と店舗情報が記載されていたこと
- 添付された画像の生々しさ
- 目撃者による詳細な説明
などが、SNSで一気に拡散される要因となったのです。情報の拡散スピードが早い現代では、一つの投稿が企業全体の信用を左右することもあると、改めて感じさせられる出来事でした。
すき家の事実発表と2ヶ月間かかった理由

ここで注目すべきは、すき家側の対応の遅れです。異物混入が報告されたのは1月21日ですが、公式な事実発表と謝罪が行われたのは約2か月後の3月22日でした。このタイムラグが消費者の不信感を増幅させる結果となっています。
私であれば、重大な異物混入が発生した場合、即時の情報開示と謝罪が望ましいと考えます。
すき家公式サイトの「お知らせ」には、調査結果や対策についての記載はありましたが、2ヶ月かかった理由については記載がありませんでした。以下はすき家公式サイトから抜粋した内容です。
発生当初に当社がホームページ等での公表を控えたことで、事後の断片的・間接的な情報により多くのお客様に不安と懸念を抱かせる結果となってしまいました。お客様および関係者の皆様に、ご迷惑とご心配をおかけしたことを改めてお詫び申し上げます。
今後同様の事態が再び発生することのないよう、全国の店舗において管理体制の一層の強化に努めてまいります。
この判断が結果として裏目に出たのも事実です。公表が遅れたことで、
- 「隠蔽していたのではないか」という疑念
- 「事実を知っていても対応しなかった」という印象
- 「企業としての透明性が欠けている」という批判
がSNSやメディア上で噴出しました。
このような結果から、たとえ調査や対策が未完了であっても、早期に情報を共有することの重要性が際立ったといえるでしょう。
なぜネズミが混入したのか?
今回のネズミ混入事件の原因について、すき家は具体的な調査結果を発表しています。異物は、味噌汁の具材をあらかじめ複数の椀に準備する工程で混入したとされており、提供前の目視確認が不十分だったことが直接の原因とされています。
実際、提供時にお椀の中にネズミの死骸が入っていたことを考えると、従業員による最終チェックが機能していなかったことが明らかです。これを防ぐためには複数人によるダブルチェックや調理場の動線の見直しが求められます。
また、背景には次のような複合的な要因の可能性も考えられます。
- 建物のひび割れ(クラック)など、ネズミが侵入しやすい構造的欠陥
- 食材を置く場所の衛生管理の甘さ
- 従業員の教育不足による手順の省略
言ってしまえば、目に見える失敗以上に、見えない部分でのルールや意識の欠如が招いた事故とも言えるでしょう。
このように考えると、単なる「異物混入事件」ではなく、店舗運営の全体的な見直しが必要な根深い問題だったのかもしれません。
公表された対策内容
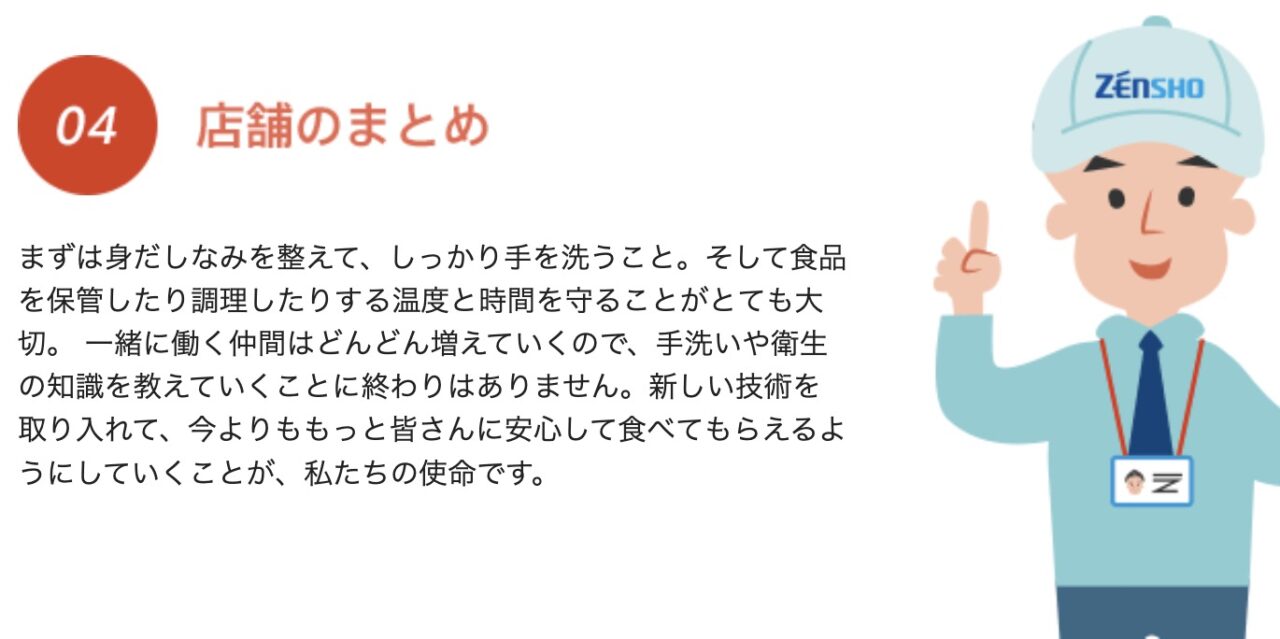
これを受けて、すき家では一連の再発防止策を実施しました。店舗の一時閉鎖を含めた徹底的な衛生検査が行われたほか、構造的な問題として指摘された「建物のクラック」への修繕も実施されたと報告されています。
具体的な対策としては以下のようなものがあります。
- 商品提供前の目視確認の徹底と再教育
- 衛生管理に関する従業員研修の強化
- 建物内部・外部の点検および修繕
- 全国店舗への指導通達による横展開
- 保健所への相談と現地での衛生チェック
特に注目すべきは、全国の店舗に対しても同様の対応を指示した点です。つまり、一店舗の問題にとどまらず、チェーン全体の衛生基準を引き上げることを狙ったものと言えるでしょう。
ただし、こうした施策が本当に機能しているかどうかは、今後の運営姿勢や再発防止の実績によって判断されます。予防策を講じるだけでなく、日常的な実践と見直しが必要になるでしょう。
また、以下の期間で一時閉店することが公表されました。
一時閉店期間:2025年3月24日(月)9:00~4月21日(月)9:00
すき家でネズミの死骸混入の波紋、異物混入に遭遇した場合の対応
- 外食業界の衛生管理の基準
- 異物混入に遭遇した場合のアドバイス
- 保健所や消費生活センターへの相談
外食業界の衛生管理の基準

外食業界が衛生管理に対して非常に厳格な基準を求められていることを強く感じます。
2021年6月からは、すべての飲食店で「HACCP(ハサップ)」という食品衛生管理手法の導入が義務化されました。
HACCPとは、「Hazard Analysis and Critical Control Point」の略で、食品の製造から提供までの各工程でリスクを洗い出し、重大な危害を防ぐために重点的に管理する方法です。この手法は、海外でもすでに広く導入されており、国際的な安全基準とも言えます。
外食店では以下のような項目が日々チェックされています。
- 調理器具や厨房の洗浄・消毒の実施
- 原材料や食材の保管温度の管理
- ゴミの処理方法と頻度
- 従業員の健康状態や手洗い・消毒の徹底
- ネズミ・昆虫などの害獣対策
このように、日常の営業活動そのものが衛生管理の連続であり、店舗ごとに管理計画を立てて記録を残すことが求められています。
一方で、こうした基準があるにもかかわらず異物混入が発生するのは、運用が形式的になっていたり、日々の忙しさの中でチェック体制が甘くなることがあるためです。言ってしまえば、基準の「ある・ない」ではなく、それを「どう活かすか」が重要なのです。
異物混入に遭遇した場合のアドバイス

もしかしたら、あなたが外食先で料理に異物が入っていることに気づく瞬間があるかもしれません。そうしたとき、感情的に行動するのではなく、冷静に対処することが大切です。
まず実行しておきたい対応として、以下のポイントを覚えておくと安心です。
- 異物の写真を撮影する(証拠として重要です)
- レシートや商品の包装を保管する
- 食べ進めずにその場で店員に伝える
- 体調に異変があれば、すぐに医療機関を受診する
- 事業者や保健所に正確な情報で報告する
このように、まずは現場で証拠を残し、記録を取ることが大切です。感情的になってSNSに投稿する人もいますが、その前に事実確認と冷静な対話が優先されるべきです。
もちろん、対応に不満がある場合には消費者センターなど第三者機関に相談するという手段もあります。仮に店舗側が非を認めない場合でも、相談窓口がサポートしてくれるので、一人で抱え込む必要はありません。
つまり、異物混入は誰にでも起こりうるトラブルですが、対応を誤らなければ適切に解決することが可能です。
保健所や消費生活センターへの相談

ここでは、異物混入のようなトラブルが発生した場合に相談できる公的な窓口について説明します。特に重要なのが「保健所」と「消費生活センター」の存在です。
まず保健所は、飲食店の衛生管理に関する監督や指導を行う公的機関です。料理に異臭・異味を感じたり、健康被害の恐れがある場合には、すぐに保健所に連絡しましょう。店舗側の対応に納得がいかない場合や、衛生環境が不適切だと感じたときにも相談対象となります。
一方、消費生活センターは、商品やサービスに関する苦情やトラブルの相談を専門に受け付けている機関です。専門の相談員が受け付け、公正な立場で処理にあたっています。
さらに、休日や祝日で地元の消費生活センターが開いていない場合は、「消費者ホットライン(188)」が利用可能です。この番号に電話すると、適切な相談窓口につながります。
相談にあたっては、次のような情報を用意しておくとスムーズです。
- 事象の発生日時と店舗名
- 購入した商品やメニュー名
- 被害の内容(健康状態や異物の種類など)
- 店舗側とのやり取りの記録(可能であれば)
このように考えると、公的な相談窓口は、問題を感情で終わらせず、冷静かつ公正に解決へ導く大切な支えになります。
すき家でネズミの死骸混入をめぐる一連の経緯まとめ
- すき家 鳥取南吉方店でネズミの死骸が味噌汁に混入する事案が発生
- 発端はGoogleマップのレビューに投稿された写真付きのクチコミ
- ネズミの大きさやリアルさからAI画像疑惑も出たが事実と判明
- SNSでの拡散によりすき家全体のイメージダウンが加速
- すき家が公式に事実を認めたのは約2か月後の3月22日
- 遅れた発表に対し「隠蔽では」との批判が相次いだ
- 原因は具材を事前に盛り付ける工程での目視確認不足
- 建物のクラックなど構造的な問題も混入の一因とされる
- 再発防止策として店舗を一時閉鎖し衛生検査を実施
- 商品提供前のチェック体制の徹底と社員教育の強化を発表
- 全国のすき家店舗にも同様の対策指示が出された
- 外食業界ではHACCPによる衛生管理が義務付けられている
- 消費者は異物混入時に写真記録と店舗報告が重要
- 保健所や消費生活センターへの相談が有効な対応策とされる

